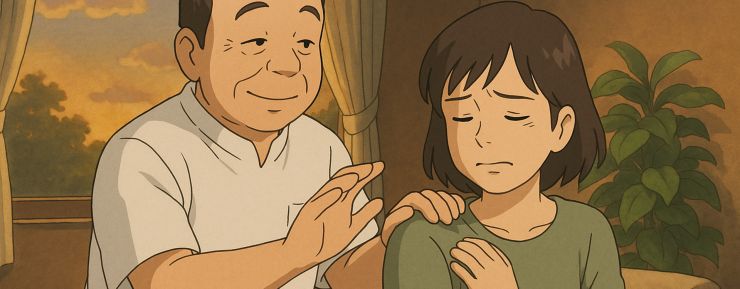冬になると不調が増える「本当の理由」とは?
11月下旬に入り、朝晩の寒さが一段と強くなってきました。この時期になると、肩こり・頭痛・倦怠感・自律神経の乱れなど、慢性的な不調が増えたと感じる方が多くなります。
一般的には「冷え」「血行不良」「気温差」といった理由が挙げられますが、AST気功ではもう一歩深い原因として、体が寒さに反応して無意識に力を入れ続けてしまう“緊張の蓄積”に着目します。
この“無意識の緊張”は自分ではほとんど気づけませんが、日々積み重なることで、冬の不調を大きく悪化させる要因になります。
身体の深層で起きている「無意識の緊張」とは?
寒くなると私たちの身体は、体温を逃がさないために筋肉を細かく収縮させます。これは生命を守るために必要な反応ですが、その反応が長時間続くと、身体の奥に硬さのクセが生まれます。
特に影響を受けやすい部位は以下の通りです。
- 首まわり(冷たい空気を防ごうと縮こまる)
- 肩まわり(筋肉が防御反応で持続的に収縮する)
- 胸まわり(呼吸が浅くなり肋間筋がこわばる)
- 腰まわり(体幹が固まり姿勢が崩れやすくなる)
このような「深い層の緊張」は、表面のマッサージではなかなか抜けません。
そしてこの深層の硬さは体のバランスを崩し、最終的に
- 呼吸が浅くなる
- 血流が低下する
- 自律神経が乱れる
- 肩・首・腰に重さが出る
- 睡眠の質が低下する
といった不調につながっていきます。
AST気功では、こうした目に見えない「深層の緊張」にアプローチすることで、身体全体の巡りを整えるという考え方があります。
冬は“力を抜けない季節” ― 頭が先に疲れてしまう理由
意外かもしれませんが、冬に最も疲れやすいのは身体よりも脳です。
理由はシンプルで、身体が無意識に緊張していると、脳はそれを常に監視し続け、調整を行う必要があるためです。
つまり、何もしていなくても脳は常に働き続けている状態
これが続くと、
- 理由のわからない疲労感
- 集中力の低下
- 気持ちが落ち着かない
- 眠りが浅い
といった「脳疲労」のサインとして現れます。
AST気功で大切にしているのは、身体の硬さをゆるめるだけでなく、この脳の負担を軽減する“全身の連動性”を戻すこと
体の連動性が戻ると冬の不調は大きく軽減する
身体がゆるむとは、単に筋肉が柔らかくなるという意味ではありません。重要なのは、筋肉・関節・膜・神経がスムーズにつながる状態に戻ること
この「連動」が回復すると、
- 呼吸が深くなる
- 身体が軽く感じる
- 血流が自然に巡る
- 頭がスッと冴える
- 気持ちが落ち着く
といった変化が現れます。
これはAST気功の施術でも非常に重視されているポイントで、身体の一部だけではなく、「全体のつながりを整える」という視点が冬の不調対策として特に有効です。
家庭でできる“冬の緊張を抜く習慣”
AST気功そのものは専門の施術ですが、日常の中で身体の負担を減らすための「緊張をためない習慣」は家庭でも取り入れることができます。
以下は、冬に特に効果が高い習慣です。
1. 肩を上げてストンと落とす「脱力リセット」
寒いと肩がすくみがちになるため、意識的に肩をふわっと脱力することが大切です。
肩を軽く持ち上げて5秒キープし、息を吐きながら一気にストンと落とします。これだけで首・肩の緊張が軽減します。
2. みぞおちをやわらかくする「ゆったり腹式呼吸」
緊張が続くと呼吸が浅くなるため、ゆっくり息を吐く時間を長く取ります。みぞおちがゆるむと自律神経が安定しやすくなります。
3. 足首を温める「下半身の巡りケア」
冬の不調は下半身の冷えから強く影響します。レッグウォーマーなどで足首を温めると、全身の力みが抜けやすくなります。
4. 1日の終わりに「胸を広げる伸び」
胸が縮むと呼吸と血流が悪くなります。寝る前に胸をゆっくり開くストレッチを行うと、眠りやすくなります。
まとめ:冬は“無意識の緊張”をためないことが健康維持のカギ
冬の不調は、冷えや気温差だけでなく、身体が無意識にためてしまう深い緊張が大きく影響しています。
AST気功の視点では、身体の連動性が崩れることで、脳や自律神経まで負荷がかかると考えます。
日常生活でできる「緊張をためない習慣」を取り入れながら、必要に応じて身体全体のバランスを専門的に整えていくことで、冬の不調は大きく改善が期待できます。
本格的な寒さに備え、今日から少しずつ身体の緊張をゆるめていきましょう。